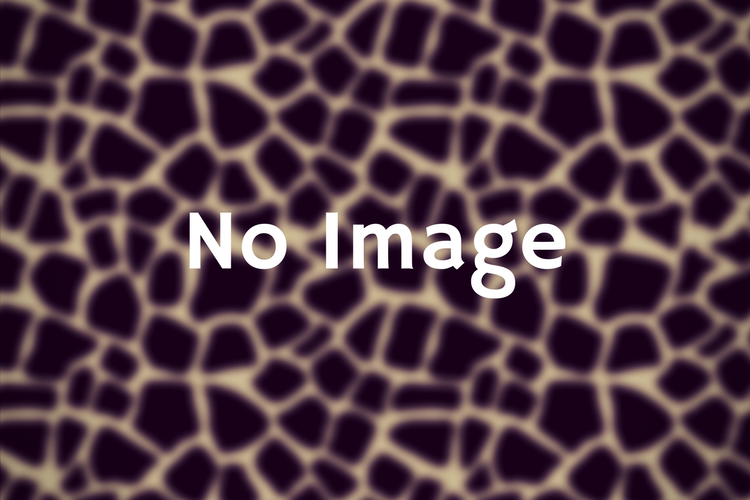【短編小説】空き缶の神様
この電柱の根元に空き缶を置くと神様が現れて願いを叶えてくれる。まだ子供だった頃、そんなことを友人たちがまことしやかに話していたことを思い出した。真夜中、コンビニに行った帰りのことである。
タイミングよく、左手にはさっき飲み終えて空になった缶コーヒーがある。右手にはすっかり短くなったタバコ。昔を懐かしむつもりで、俺はタバコを缶に入れ、電柱の根元に置いた。
缶の口からはタバコの煙が細々と漂っている。あの頃の噂を信じているわけではないが、なんとなく両手を顔の前で合わせ、願い事をしてみる。
「金持ちになりますように」
そう心の中で唱え、目を開ける。見ると、缶の口から出る煙がさっきよりも太くなって次々と立ち上がっている。顔をあげると、ちょうど目の高さ辺りで煙が立ち込めていた。
何事かと思い呆然としていると、煙はもくもくと形を変え、人の姿を作り始めた。現われたのは長いひげを生やした老人だ。彼はふわふわと浮かぶようにして空き缶の少し上に立った。
目の前の出来事に言葉を発せずにいると、老人が声をかけてきた。
「私を呼んだな」
少し厳しい口調だった。よく見ると不機嫌そうな顔をしている。俺はしどろもどろになりながら言った
「あなたは一体……?」
「呼び出しておいて何を言っている。私は神だ」
めまいを感じた。普段なら無視して家へ帰るところだが今はそうもいかない。この老人が煙から作られていくのを目の前で見たのである。神様ではないにしろ、何か神秘的な存在であるに違いない。俺はようやくのことで声を絞り出して訊ねた。
「では、あなたは願いを叶えることができるのですか?」
「もちろんできる。人間が喜ぶ姿を見ることは神である私にとっても幸せなことだ」
老人は答える。その言葉を聞いた瞬間、脳裏に一人の女性が浮かんだ。あこがれだったあの女性。学生時代、親しい仲だったにも関わらず、自分の臆病のせいで彼女に思いを伝えられなかった。その後悔がずっと心に残っていたのだ。願いをかなえてもらうならこれしかないと思った。今さら思いを伝えてどうにかなるものでもない。だがもう一度、彼女に会ってあの頃のように楽しい時を過ごしたいと思った。俺はつい前のめりになった。
「では私の……」
「いや、それはだめだ」
老人の言葉は早かった。当然、俺は納得がいかなかった。ほんの少しの時間、彼女に会わせてくれればいいのだ。なにも彼女の人生に影響を与えたいわけではないのに、なぜ断られなければいけないのか。俺は不満に思い、訊ねた。
「どうしてだめなのですか」
「理由は簡単だ。私はお前のことが嫌いなのだ」
「わかりません。あなたと私はたった今、会ったばかりです。私はあなたに嫌われるようなことはなにもしていません」
俺がそう言うと、老人は黙って自分の足元を指さした。俺が飲み干したばかりの空き缶が立っている。老人は言った。
「私はお前のように平然とゴミをポイ捨てする輩が大嫌いなのだ。そのような者の願いなど叶えてたまるか」
そう言うと老人は威嚇するようにキッと歯をむき出し、再び煙となって消えた。
だったら空き缶から現れなければいいのに。人気のない道でその言葉を飲み込む。面倒な神様もいたものである。俺は少しがっかりしながら、空き缶を拾って家へ帰った。