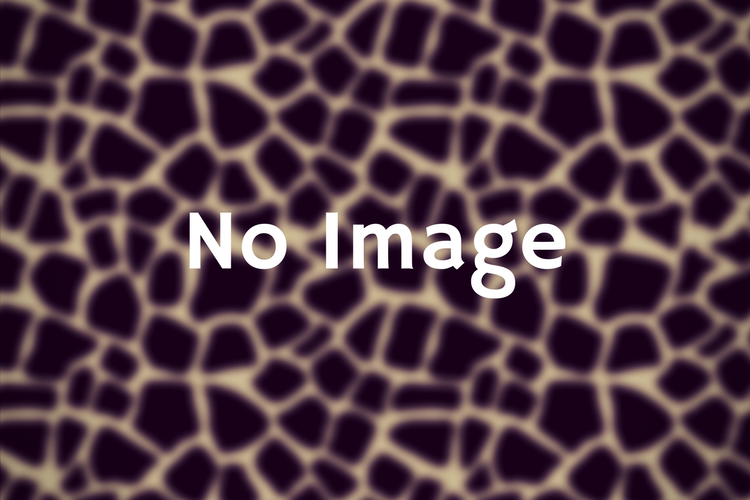【短編小説】男女
先を歩く彼女が振り返る。真っ黒な長髪に凛とした顔。ふくらみの少ない体をひねるその姿はとても魅力的だった。思わず見とれそうになるが、自制を働かせて手元のスマホに視線を落とす。そのまま操作する振りをしながら歩を進める。彼女の目に自分はどう映っているだろう。顔を伏せるタイミングが変だったかもしれない。ちゃんと通りすがりのサラリーマンに見えているだろうか。どうにも自分の挙動に自信が持てず、不安が胸をよぎった。
怪しく思われたのではないかと慎重に顔を上げると、彼女は再び前を目指して歩いていた。黒髪が誘うように左右に揺れている。
スマホをスーツのポケットにしまい、彼女の後ろをついていく。週末の昼前。この時間帯の彼女の行動はとっくに知っている。もうじき交差点を右に曲がり、薬局の隣のスーパーへと入るのだ。
果たして、彼女は交差点を右折した。スーパーへ入っていくのを確認し、俺はスーパーの前を通りすぎた。店の中というのは危険である。商品を選ぼうと彼女が視線をさ迷わせる際に、その視界に俺が入ってしまうかもしれない。この姿はついさっき見られたばかりなのだ。そう何度も彼女の前に現れるべきではない。今日はこの辺りで止めておいた方がよさそうだ。俺は自宅へと戻った。
部屋について着なれないスーツを脱ぎ捨て、壁に貼られた一枚のコピー用紙に目を向ける。そこには一週間の予定表が書き込まれていた。彼女のあとをつけ、半年かけてこつこつと作り上げた予定表。これは彼女の行動を記したものだ。俺はそれを眺め、ひとり満足感に浸った。
今日と同じ曜日の欄を見る。午前9時、外出。公園を散歩したあと喫茶店へ。喫茶店の次はスーパーで買い物。その後、自宅へ戻る。今ごろ彼女は家路を歩いているはずだ。午後は服を買いに行くか、ジムに行くかして過ごすのだろう。
さきほど、食い入るように眺めていた彼女の歩き姿を思い浮かべる。リズミカルに揺れる肩に軽やかな足取り。あれは自分への愛のメッセージなのではないか。そう思いたくなるほど、彼女は魅力的だった。
彼女を初めて見たのは今日のようによく晴れた日だった。
その頃の俺の日課といえば、目的なく町をふらつくことだった。社会となんらのつながりがない、いわゆる無職と呼ばれていた俺はひたすら時間を浪費していた。刺激のない、平坦で退屈な日々だった。
歩く道順が決まっていたわけではない。ただふらふらと歩いて、偶然通りかかった美容院の前で彼女を見つけた。軒先にしゃがみこみ、プランターに並べられた花たちを眺めていたのだ。その様子を見て俺は彼女に一目惚れしたのだ。
恋がこんなに突然訪れるものだとは思わなかった。もっと中高生に訪れるものなのではないか。青春などとっくの昔に終わったおっさんの俺が一目ぼれがをするとは思わなかった。不覚だった。
すれ違う若者に「なに一目ぼれしてんだよおっさん」とやじられたら頭を下げて謝ってしまうかもしれない。
彼女は花に夢中になっていた。俺にはそんな彼女に声をかける勇気などなかった。母親以外の女性と話をしたのはずいぶん前のことである。一方で、瞬く間に沸き上がる彼女への思いを抑えることもできない。やむを得ず、俺は彼女のあとをつけた。慣れない尾行に戸惑いながら、その日は彼女の家を突き止めることに成功した。それ以来、彼女を追うことが俺の習慣となったのだ。
こうして俺の毎日は甘いものとなった。彼女との出会いはまさに奇跡。一生のうちで、まさか自分が一目惚れをするとは思わなかった。人生とは予想外のできごとが起きるものだと偉い人が言っていた気がする。こんなことが起きるなら俺の人生も案外悪くない。
壁の予定表から目を離し、俺は日々の充実感に感謝した。
次の日は平日だった。彼女は平日の朝にはいつも駅へと向かう。仕事に行くのだろう。私服で出社しているということは、そこそこ自由な社風なのだろうか。
いつものように彼女のすむマンションの前で待ち伏せ、彼女の後ろをついていく。駅は人で溢れ返っていた。
平日は、彼女が改札をくぐったところであとを追うのはやめる。切符を買う金がないからだ。
普段なら彼女は改札の前までまっすぐ歩いていくのだが、今日は違った。途中でトイレに寄ったのだ。思えば今まで彼女がトイレに入る場面に遭遇したことはなかった。何か新たな発見があるかもしれない。
期待を込めて彼女を見ていると、こともあろうに、彼女は男性用トイレに入っていった。間違えたのだろうか。
俺はトイレの入り口に立ち、スマホをいじり始めた。彼女が間違えて男性用トイレに入ったのなら、当然彼女は恥ずかしそうにトイレから出てくるはずである。彼女に好意を寄せるものとして、そのときの彼女の表情を見逃すわけにはいかない。こうして入り口で待っていれば、恥ずかしげに出てくる彼女の顔が拝めるはずである。
やがて彼女が出てきた。しかし表情は案外普通だった。俺は少し残念に思いながら、彼女について歩き出した。
ところが、数歩歩き出したところで、彼女に近づいていく者がいた。たった今、男性用トイレから出てきた男だ。彼は言った。
「ハンカチ忘れてますよ」
「あ、すみません」
振り返った彼女が応える。その声がやけに低く、また力強かった。その違和感になぜか悪寒が体中を駆け抜けた。
不思議に思い、俺は少しだけ二人に近づいた。彼女の顔をちらりと盗み見たとき、俺はあることに気づいた。彼女の口の周りにはうっすらと青髭が生えていたのだ。
俺は思わず膝から崩れ落ちた。彼女ではなかった。こいつは女装した男だったのだ。