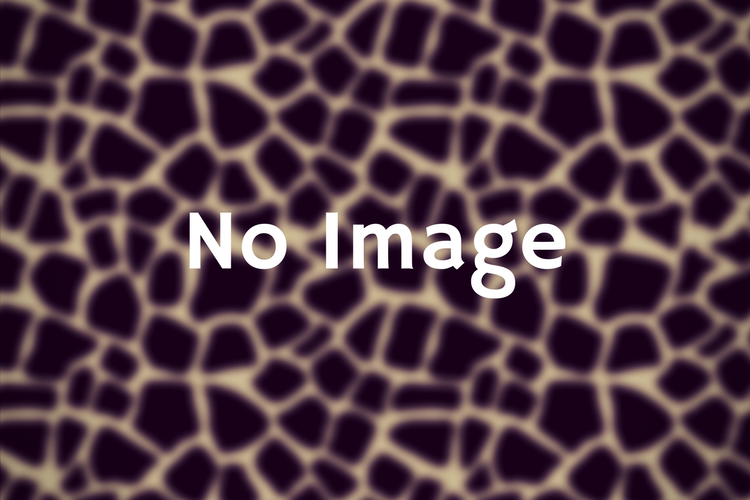【短編小説】押し入れ、赤い屋根の、炬燵の中
押し入れ
机の下に鍵が落ちていた。
見るからに安物の鍵。一体いつからそこにあったのだろう。僕はそこに鍵があると気づかないまま、どれだけの時間をその部屋で過ごしたのか。
この部屋の中に、鍵穴の付いたものはそう多くない。机の引き出し、部屋の扉、貯金箱。この鍵が一体どの鍵穴に遭うのか、僕はひとつひとつ確かめた。
しかし、どれも合わない。もしかしたらこの鍵は僕のものではないのかもしれない。そう思ったとき、あの小物入れを思い出した。
まだ僕が幼かったころ、祖母からもらったあの小物入れ。人形やきれいな小石をしまっておくのに使った小物入れ。あの頃の僕にとって間違いなく宝箱だった。その鍵を最後に開けたのはいつだったろうか。
僕は家中を探し回った。宝箱はいったいどこへいったのか。
見つけたのは庭の隅にひっそりと佇んでいる物置の中だった。僕はさっそく鍵を開けた。
出てきたのは、当時の僕が大切にしていたガラクタ。どれもこれも思い出の詰まったガラクタだった。僕はそれを部屋に持って帰り、押し入れの中にしまった。
赤い屋根の
電信柱の根元に一匹の猫がいる。まっくろな体と頬のあたりの白い毛並みが対照的だ。彼はもう1時間ばかりそこに居座っていた。
目の前を年老いた男が乗った自転車が横切る。それを合図にしたかのように、猫はゆっくりと歩き出した。
道なりにまっすぐ進む。突き当りの角を右に。3軒先のコンビニの角は左。
猫は立ち止まることなく歩き続ける。やがて、ごくありきたりな、赤い屋根の一軒家にたどり着いた。猫はその家の門をするりと抜ける。
その家に住むのは4人の親子。夫は仕事、子どもたちは学校にいるため、今この家にいるのは妻ひとりだけだった。
妻が猫の姿に気づいた。彼女は台所から缶詰をひとつと小さな皿を持ってきた。猫が妻に近づいていく。
皿の上に缶詰の中身があけられた。一瞬の間も置かずに口をつける猫。2年前から続く彼らの密会である。
炬燵の中
すっかり雑誌に夢中になっていた。コンビニの外ではいつの間にか雪が降っている。初雪だった。
今朝の天気予報を思い出す。寒気が入り込んできて寒くなると確かに言っていたが、雪が降るとは思わなかった。外はいっそう寒そうに見える。こんなことなら外出しなければよかったと、今になって後悔した。
だがいつまでも立ち読みをしているわけにはいかない。時計を見ると、コンビニに入ってもう30分以上経っている。雑誌を棚に戻し、雪の降る薄暗い外へと出た。
雪はアスファルトに落ちるそばから溶けていく。おそらく積もることはないだろう。少し安心して家路を歩いた。
少し風が出てきたようだ。冷たい空気が頬をなでる。風が服の中にまで入ってくると無意識に体が震えた。その度に全身から熱が逃げていくような気がする。本格的な冬はまだ先だというのにずいぶん寒い。今年の冬を乗り切れるだろうかと不安がよぎった。
ようやく家に着いた。玄関を開けて中に入り、居間の炬燵に電源を入れる。全身を潜り込ませてじっとしていると、炬燵の中の温度が上昇していく。寒さから解放された体がほぐれていくのを感じた。