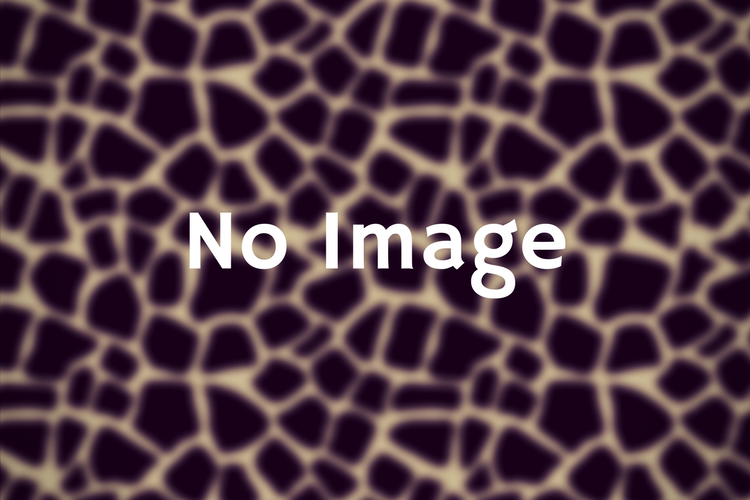【短編小説】うわさ
私の地元には怪談がたくさんある。例えば、住民の中には妖怪が紛れていてみんなと同じように生活しているとか、夜中の12時ちょうどに町はずれにある神社の境内に立っているとあの世へ連れて行かれるとか、国道の歩道橋には地縛霊がいて憑りつかれるとなぜかその歩道橋から飛び降りずにはいられなくなるとか。そういった噂が、数え上げればきりがないくらいこの町にはある。私たちは子供の頃、それらの話を誰からともなく聞き、噂し合った。どれもどこかで聞いたことのあるような話だけど、当時はみんな怖がって聞いていた。
高校を卒業して4年目の夏、私は久しぶりに仲の良かった男女3人と集まることになった。高校時代によく通ったカラオケ店で私たちは昔話に花を咲かせた。当時の思い出が次々によみがえり、私たちの話はどんどん弾んだ。日常のこと、体育祭や文化祭などのイベントでの出来事。その場の誰もが懐かしさに酔いしれ、収拾がつかなくなり、いつのまにか話題は小学生の頃までさかのぼっていた。高校に入るまでは全く接点のなかった者たちの昔話である。かなりとっ散らかった、めちゃくちゃな会話だったが、懐かしさでいっぱいだった私たちはそれなりに盛り上がった。
そんな中、数少ない共通の話題となったのが怪談話だった。
「小学生の頃、怪談が流行らなかった?」
「流行った。なんかこの町はその手の話が多い気がする」
「神社の話とかでしょ?あとは歩道橋がどうとか」
「そういうのそういうの。学校の帰りによく肝試ししたよ」
「肝試しって普通は夜中でしょ」
「そういえば夜の神社に友達と行ったことあるよ」
「へー、どうだった?」
「特に何も起きなかった」
「やっぱりそうか」
「まあ12時に行ったわけじゃないけど」
「なんだ、じゃあだめじゃん」
「一番好きなのはあれだな、『酒飲みおやじ』」
「そんなのもあったねぇ」
酒飲みおやじ。山の中にあるトンネル付近に現れるという幽霊の話だ。
20年ほど前、夜中にそのトンネルの手前で一台の車が道路を飛び出し、山すそを転がり落ちるという事故があった。運転者は私たちと同じ市内に住む中年男性。彼は遺体で発見された。大の酒好きだったらしく、彼が乗っていた車からは大量の酒瓶が見つかった。大方、酒を飲みながら運転して事故を起こしたのだろうというのが大人たちの見解だった。
その事故があって以来、現場の近くでは夜になると中年男性の幽霊が出るそうだ。彼は遺体で見つかった時と同じ血にまみれたボロボロの服を着て、おぼつかない足取りでのそのそと歩き回り酒を探している。すれ違うと誰かれ構わず「酒を持ってないか」と聞いてくるという。なんと動物にも聞いて回っているという話まであるから笑いものだ。
酒飲みおやじは酒を受け取ると歩いてどこかに消えていく。酒をもらえない場合は相手を呪ってひどい目に合わせるというのだ。ちなみに動物が呪われることはない。呪われるのはあくまで人間だけである。小学生が噂するにふさわしい中途半端な怪談話だが、こんな話でも当時は心底怖がったものだった。
「あのトンネルは山の中にあって遠いから一回も行ったことないな」
「たしかここから車で30分くらいだっけ」
「それくらいだな」
「小学生じゃ行けないよね」
「親に『行ってみたい』って頼んだことあるけど断られたな」
「じゃあ今夜行かない?免許持ってるし」
「マジ?」
「車は親から借りればいいよ」
「いいね。楽しそう」
「行こう行こう」
そうして私たちは酒飲みおやじのトンネルへ肝試しに行くことになった。
深夜2時。私たちは隣の市との境にある山の中を車で走っていた。この道路は隣の市へ通じる唯一の道路であり、きれいに舗装されている。日中の交通量はそこそこ多いが、さすがにこの時間ともなると他に車は通っていない。辺りは真暗で、私たちの車のヘッドライトと、ときおり現れる外灯のほかに明かりはなかった。
しばらく走っていると、夜闇のむこう側に、例のトンネルのぼんやりとしたオレンジ色の照明が見えた。私たちは車を停めて懐中電灯だけ持って歩きだした。時おり涼しい風が吹き、その度に周囲の草木のこすれる音がした。懐中電灯の明かりを頼りに歩いているうちに、トンネルを抜けてすぐのところにあるカーブミラーまで行って戻ってくることに話が決まった。
トンネルの姿がはっきりとしてきた。途中で曲がっているので入口からは向こう側の出口が見えない。巨大な蛇が獲物を飲み込もうと大きく口を開けているかのようだ。
私たちが生まれる前からあるこのトンネルは、壁の所々にひびが入っている。トンネルの前に立ってふと横を見ると、ガードレールの色が一部だけ変わっていることに気づいた。事故が起きたあとにこの部分だけ新しいガードレールに取り換えたのだろう。私たちはガードレールを横目にトンネルに入った。
トンネルの長さは700mほどある。中は照明でオレンジ色に照らされていて、薄暗かった。とても静かで、私たちの歩く音と話声はトンネルの壁に吸い込まれていくようだった。
出口が見えてきたころ、向こう側から人が入ってくるのが見えた。
「あ、人だ」
「どれ?」
「ほら、真正面」
「ああ本当だ。ひとりでなにしてるんだろう」
その人はとてもゆっくり歩いていた。体を左右に大きく揺らして歩く姿は、薄暗いトンネルの中でも目立って見えた。
トンネル内を進むにつれ私たちの間の距離は縮まり、だんだんその人の姿がはっきりとしてきた。背はそれほど高くないが、体格はがっちりとしていて遠目からも男性だと分かった。赤と白の割合が半々くらいのシャツを着ていて、右足を引きずりながら歩いていた。
さらに近づいて彼の顔が見える距離になった時、誰かが小さく息をのんだ。男性の顔は血で赤く染まっていた。
「大丈夫ですか」
一人が駆け寄った。私たちも彼を追いかけるようにその男性に近寄った。私たちがそばに行くと男性は足を止め、何も言わず私たちを見つめた。血の気のない青白い顔とは対照的に目が血走っていた。
「なにがあったんですか」
「救急車を呼ばないと」
「動かない方がいいですよ」
見るからに重傷を負った男性を前に、私たちはかなり動揺した。
だが、慌てて声をかける私たちをよそに、男性はかすれた声で「酒を持ってないか」と言った。私たちはそれに答える余裕もなく、男性を座らせようと手を貸したり、救急車を呼んだり、男性を助けようと必死だった。すると、男性は今度は私の肩に手をかけ、もう一度「酒を持ってないか」と尋ねた。
私が「いえ、持ってないですけど」と答えると、彼は私以外の面々にも「酒を持ってないか」と聞きだした。誰も酒を持っていないことがわかると、私たちに顔を向けたまま黙りこくった。私たちもつい動きを止めて彼を見つめた。
彼は微動だにしなかった。どうしたのかと見守っていると、彼の血走った両目にじんわりと赤い色が広がっていくのが見えた。赤はだんだん面積を大きくし、やがて両目が真っ赤に染まった。途端に私の視界は赤に覆いつくされ、他に何も見えなくなった。
トンネルの中は相変わらず静かだった。何が起きたのかと辺りを見回しても、視界は赤く染まっていて何も見えない。突然の出来事に戸惑っていると、近くで他の3人が悲鳴をあげたのが聞こえた。同時に、3人が駆け出す足音。私は驚いたが、彼らが来た道を引き返しているのだと直感し、彼らについていこうと走った。
真っ赤な視界の中、3人の足音を頼りに走っていると、突如視界が元に戻った。そこはトンネルの外だった。前方を見ると、3人が車を目指して走っている。振り返ると、トンネルは何事もなかったかのように佇んでいた。私は3人のあとを追った。
私たちは急いで車に乗り込み、その場から引き返した。
山道が終わって街の明かりが見えてきたころ、ようやく私たちの間に会話が起った。私たちは堰を切ったように話し始めた。誰もが心底怯え、冷静さを失っていた。
「なんだったのあれ」
「知らないよ」
「怖かった」
「錯覚じゃないよね?急に目の前が真っ赤になった」
「錯覚じゃないでしょ。全然何も見えなかった。手探りで走ったよ」
「それよりあの人何をしようとしたんだろう。俺、急に首をつかまれたよ」
「私は上から頭を押えられた」
「俺は足。折られるかと思った」
私は黙った。他の3人はどうやらあの男性に体を触られたらしい。私はなんともなかったのに。なぜ私は何もされなかったのだろう。
その日はそのまま各々の家へ帰った。せっかく久々に4人で集まったというのに、後味の悪い別れになってしまった。私たちはまた集まろうと約束した。
それから一週間が過ぎた頃、3人から連絡が入った。どうやら3人とも同じ時期に体の不調に見舞われてしまったらしい。ひとりは、最近、寝ている間に突然息苦しくなって起きることがあるという。なんでも、首を絞められるような感覚がすると言っていた。おかげで近頃は寝るのが怖く感じているそうだ。別のひとりは頭痛がひどいという。普段はなんともないのだが、突然割れるような頭痛がして、立っていられないほどだとのことだった。病院で診てもらったものの、特に異常は見つからなかった。もうひとりは両足を複雑骨折した。ある日、買い物に行こうと道を歩いていたところに車が突っ込んできたのだそうだ。当面は車いすでの生活になると嘆いていた。みんな口々に「酒飲みおやじの呪いだ」と言っていた。
私はというと、特に異変は起こらなかった。何の問題もなく毎日を過ごしている。
どうやら「酒飲みおやじ」のうわさも嘘ではないらしい。この町の怪談の中には真実を伝えているものがいくつかあるのだなと思った。